
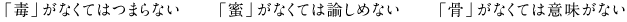
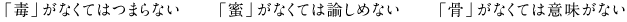
「この本が出てしまうと、また純歌さんが週刊誌に追い回されたり、あるいはネットでバッシングを受けたりするかもしれませんよ。それでもし……」
ザ・ドリフターズの仲本工事さんと12年近く交流のあった窪田正二さんという男性が、出版会議でそのように発言したとき、仲本さんの妻、三代純歌さんは「それでも私は闘います。もう失うものはないから」と言い切った。
週刊誌によるバッシングですっかり衰弱してしまい、ライターや歌手、タレントなど周囲の人たちが家を訪ねて彼女を見守ってきたころには、とても純歌さんはそんなことを言える状態ではなかったと窪田さんらは証言する。周囲の仲間は、いわば命の危険を察知して助言するゲートキーパーの役割を担ってきたようだった。
あらためて純歌さんの決心を聞いた翌日の2023年11月14日。旧ジャニーズ事務所の性加害問題で被害を受けたと名乗り出ていた男性が、SNSなどで誹謗中傷されたことを苦に自殺していたというニュースが駆け巡った。命が奪われて初めて、被害の深刻さが露わになるというのは皮肉なものである。
本書、『笑顔の人―仲本工事さんとの真実』(三代純歌著)の本文にも登場する、仲本工事夫妻に対する週刊誌バッシングとは具体的には、どういうものだったのか。
「『週刊新潮』の暴走に、その他の週刊誌が安易に追従して彼女を追い込んだ」というのが、この手記を手伝い、話を持ち込んできた元新聞記者であるジャーナリスト、依光隆明さんの見立てだった。その追い込まれた側の主張を世に出すことで、社会に一石を投じたいのだという。依光さんのようなジャーナリストが聞き取っているのであれば、相応の意義があるのだろうとこの出版を引き受けた。彼の目の確かさ、面白さ、手腕などを知って既に30年以上が経つ。その歳月もまた彼への信頼に繋がっていた。
問題の発端は2022年10月13日に全国書店で発売された『週刊新潮』の記事で、女性週刊誌までもが、その記事を引用、便乗して記事を書きSNSをかなりヒートさせていた。
近年、オールドメディアと揶揄される週刊誌の発行部数というのは、全体的に右肩下がりである。『週刊新潮』の場合も、御多分に洩れず2012年の約58万部から約30万部にまで落ち込んではいる。しかしインターネット上の『デイリー新潮』のPV(ページビュー)は桁違いに多く、月間PVは1億を超えている。ここから記事の一部がいち早く拡散されるため、普段は、週刊誌などは手に取らない層も焚き付けられる。デジタル・タトゥーと呼ばれて久しいが、ひとたび記事がインターネット上に拡散されると半永久的に、まるで入れ墨のように残されてしまう。純歌さんの受けた被害が甚大になったのも頷ける。
話を聞いただけでも週刊誌が寄って集って食い物にした状況が見て取れた。「まさに四面楚歌ですね」との言葉が口を突いて出たほどだった。
問題の発端となった『週刊新潮』を開くと、『ドリフ「仲本工事」を虐げる27歳下「モンスター妻」』という、大仰な特集タイトルが目に飛び込んでくる。なんと4ページのトップ記事である。 純歌さんが、モンスター妻であり彼女が仲本さんを虐げているという筋書きなのだが、どれほど彼女が高齢の仲本さんにDVやパワハラを行ったのかと読み進めても、それはどこにも書かれていない。それもそのはず純歌さんはその現場にはいない。
彼女が仲本さんを虐げている、というのはあくまで『週刊新潮』の感想である。つまり記事が指摘しているのは、仲本夫婦の家がひどく散らかっており、そこに片付けるべき若い妻がいないではないかという、いわば「不作為の罪」を問うているのだ。
純歌さんは公人(公務についている者)でないので公序良俗違反ではなく、まして犯罪を犯しているわけでもない。首相の秘書官で息子でもある人物が、公邸で親類を招いて忘年会を開いて騒いでいるのとはわけが違う。
このような公益性のない話で、名指しで、有名週刊誌に「モンスター妻」と書かれ、ネットで拡散されたのであれば書かれたほうはたまらない。 本来であればすぐに名誉毀損罪で刑事告訴すべきだったろう。そうすれば書いた記者や編集者までをも罪に問うことができた。だが名誉毀損というのは親告罪であり、親告罪の告訴は犯人を知った日から6カ月の間しかできないため「時すでに遅し」ということになる。
メディアに少しでも関わっている者なら反撃の手段はすぐに思いつくに違いないが、普通はそこまで気が回らないから、こういった暴走に歯止めをかけられない。 民事で訴えるにしても損害および加害者を知った時から3年で請求権が消滅してしまう。もし訴える覚悟があるのならば迅速にやる必要があると思われた。 それにしても、発端となった『週刊新潮』の記事のずさんさには驚くばかりだった。
仲本さんの娘さんの証言が歪曲されているなども氷山の一角で、あまりに内容がひどいのだと関係者は口を揃える。
「留守のときに侵入されたのではないか」と純歌さんのマネージャーである天野若雄さんが疑うのも無理はないと思われた。 百歩譲って、この記者が訪れた日に仲本さんが在宅していたとする。だが少なくとも仲本さんは複数回の取材に対して「帰ってくれ、と終始、怒鳴っていた」と、この記事が自ら明かしている。本人を激怒させるほど執拗な週刊誌取材だったという証左であろう。「仲本さんが撮影の許可など出すはずもない」という純歌さんや天野さんの主張のほうが、はるかに説得力がある。掲載された写真が、いつ撮影されたものであるかの記載もない。
その無許可写真と歪曲された証言のある記事を、しかも「ゴミ屋敷」、「モンスター妻」として、『週刊新潮』は、約30万部も印刷して販売し、あるいは月間PV が1億を超えるウェブサイトで公開しているのだから、これがもし大手新聞の仕事ならば、社長の首が飛んでもおかしくない大事件になっただろう。
高齢化社会の今日、高齢者の自宅が片付かない家など相当な数あるだろうが、芸能人の住処だからといって、それを週刊誌でいきなり暴露し写真や証言を並べて報道することにどれほどの意味があるのかは議論があるに違いない。
純歌さんとの関係に「不満はなく満足している」と各所で語っていた仲本さんだが、純歌さんがいないときに、一人でどこまで自分の部屋の掃除などができたかは、たしかに疑わしい。
その点でいうと、手記が書き上がってから分かったことが、いくつもあった。 仲本さんは、純歌さん不在のときに、出入りしていた40代の女性にアルバイト料を支払って部屋の掃除や犬の散歩を頼んでいた。この女性こそ、仲本さん夫婦に代わって衛生面やペットの管理を行っていた事実を述べることのできる人物である。
ところがそんな話は、どの週刊誌にも1行たりとも出てこない。
なぜか? それもそのはず、その女性は自ら週刊誌に「ゴミ屋敷」のネタを売り込んでいたからである。金をもらって掃除をしていた女性がゴミ屋敷を演出するというマッチポンプに相乗りして、週刊誌は、内部関係者の話を肉付けした。元ネタがあまりに弱いにもかかわらず、話を盛り過ぎたきらいがあった。
芸能人だから写真が公開されても我慢すべきでは、というのは的外れだ。2016年の東京地裁判決が、有名歌手の自宅内の人物を許可なく撮影して写真を掲載した出版社に550万円の損害賠償の支払いを認めている。芸能人にプライバシーがないわけではない。
前述のように、交通事故に遭って仲本さんが死亡したのちにも多数の週刊誌のバッシングは続く。なかでも『女性自身』の一連の記事はかなりひどいと純歌さんは涙ながらに訴えた。記事に登場する証言者の多くは匿名であるため、自分ではないと否定されれば、追及する方法は法的手段しかないというのが関係者の話だった。
ちなみに、2006年のアメリカの日本法人が所得隠しをしたとの報道で、記者が裁判で取材源に関する証言を拒絶したケースがあった。このとき最高裁は、「報道関係者は原則として取材源にかかわる証言を拒絶できる」としている。こういう流れで「取材源の秘匿」は正当化されてはいるが、それをいいことに、多くの媒体で証言の誇張や歪曲が常習化されている。
前述の窪田さんや天野さんなどは、フルネームでコメントすることを厭わない。つまりリスクを引き受ける覚悟がある人の証言である。そこに一定の信憑性、真実味を感じるのは自然なことだ。取材源の秘匿に守られた匿名コメントの意義は認めつつも、こちらの迫力は、『週刊新潮』の記事の力をはるかに上回った。
『女性自身』に掲載された写真を見て、天野さんは「捏造された写真が掲載されたのではないか」と首を傾げる。一枚目の写真と二枚目の写真では明らかに写っている物の位置が変わっているなど、いくつもの根拠を挙げ、合成されたか、意図的に被写体を動かした演出撮影が行われているというのだ。たしかにやらせ写真に見える。
さらにこの件では、窃盗も起こっていた。 事実、仲本さんが交通事故に遭った2022年10月18日から告別式の同月23日までの間に、純歌さんが経営していた店と目黒区内の自宅に設置していた三台の防犯カメラが取り外され、その中のカード(記録メディア)が盗まれるという事件が起こって、純歌さんは警察に駆け込んでいる。被害届を受けた警視庁碑文谷警察署は、純歌さんの自宅を捜査して残された指紋を採取して、同年12月22日に被害届を受理している。
この窃盗には証拠を隠滅しようとした犯罪の可能性が濃厚である。 このことを記事にした写真週刊誌『FRIDAY (フライデー)』は、一連のバッシング報道と結びつけながらも言葉を慎重に選びながら、『降って湧いたようなミステリー事件……。はたして犯人は見つかるのだろうか』『すっかり定着してしまった「悪女」のイメージを覆すことはできるか』などとの所感を述べるにとどめている。
一連の週刊誌でのバッシングには、デリカシーのない一方的な攻撃が認められた。非常識な取材、報道の自由を逸脱して名誉を毀損し、プライバシーを侵害したり個人の尊厳を傷つけたりする記事が多かったという依光さんの話には共鳴できた。 かたや書かれた側の仲本さんや純歌さん、支援者らは懸命なコメントを出してはいるが、反論できる機会はほとんど失われているということも判明した。 前述の『FRIDAY』が書くように、すでに定着させられてしまった「悪女」のイメージを覆し、純歌さんが芸能人として活躍できる状態に戻ることは時間がかかるのかもしれない。
多勢に無勢ではあるが、純歌さんには、仲本さんへの思いを綴っておきたいという意向があり、出版に踏み切ったものであることを付記しておきたい。
文責/木村浩一郎