
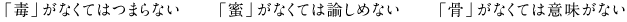
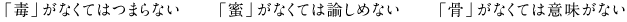
本文敬称略
かつて、宇留間和基という元アエラの編集長、元朝日新聞出版社長の本を当社で刊行した。
彼と知り合うきっかけとなったのは、別の著者の出版記念パーティの時だったと記憶している。
僕の場合には人様に自慢できるような人脈はないものの、ライターやジャーナリスト、新聞や雑誌の記者で気が会う人とは、20年、30年以上の付き合いになる人が多い。朝日新聞社との関係でいえば、僕が、広告ライターとして広告プロダクションに勤務して、タレントや文化人を相手に、広告やインタビュー記事を書いていた頃の関わりもある。
ベルリンの壁が崩壊した1989年末ごろから90年にかけて、僕は、朝日新聞に掲載するAERAの広告を幾つかつくったことがあった。ベルリンの壁の穴を抜けて出会った、敵対していた東ドイツと西ドイツの兵士が、肩を組んで映った写真を起用したものだった。
10年以上前に、僕は宇留間にそんな話をした。宇留間は、そのころ記者としてヨーロッパで取材していたのだと、目を細くして語ったのが印象深かった。
僕自身は「朝日新聞」という企業が好きかと聞かれれば決してYESとは言えない。
理由はいくつもある。「朝日らしさ」という、いわばジャーナリズムを標榜しながらも、組織としてのご都合から報道の原理原則を逸脱するやり方などを感じた時には賛同できないことがいくつもあった。僕はそんな持論さえ宇留間にもぶつけたことがある。
ほかの朝日の人間と違い、宇留間はほとんどジャーナリズムを語らない。僕にとっては、それが彼の強みでもあり弱みでもあると勝手に思い込んできた。
最近、むしずの走る出来事があった。
2021年8月23日に、前出の宇留間和基の書いた本、『編集の教科書』に対して、アマゾンに大鹿屋というネームでレビューが投稿されていた。
レビューの内容は、次のような短いものである。
「あまりにスカスカな内容なのに驚いた。かなりレベルが低い。本人も薄っぺらな人だが、書いたものもそうだった。これでよくAERAの編集長や朝日新聞出版の社長がつとまったなと驚きだった。よくもまあ、こんな人をJーCASTも雇ったものだと衝撃を覚えた」
本の内容を、読者が「スカスカ」と書こうと「レベルが低い」と書こうと、僕は気にならない。所詮、レビューとは読者による感想である。どれほど低い評価があっても、それが読者の感じた評価なのだからいちいち目くじらを立てるべきではない。
さらにこのレビューは、本そのものではなく、「薄ぺらな人」という人物像に焦点を当てており、「AERA編集長」や「朝日新聞出版社長」、そして現在の勤務先「J-CAST」について書いている。だがこれも公開された情報である。
一方で、宇留間が書いたこの『編集の教科書』という本には、前述のような宇留間が、大上段に構えてジャーナリズムを語らない姿勢、すなわち「朝日らしくない」という評判そのものを逆手にとって「朝日新聞社で最も軽いと言われた男がつくった」ということをキャッチコピーに添えていた。これは僕のアイデアでもあり、当然のことながら宇留間が承知したものである。
であるがゆえに、読者が、宇留間を「軽い」と書こうと「薄っぺらい」と書こうと、それは本望なのである。
宇留間の書いた本書には、どんな良書であっても、その打ち出し方、見せ方によっては反響が得られない、ということや、記事や文章は、内容が大切とはいえ、タイトルや見出しがことのほか重要である、ということを力説したものであり、編集にもマーケティングの考え方を生かすべきだといったことが主軸となっている。
それゆえに、正面から権力や不正に向き合い、それと戦うジャーナリストから見れば、半ばチープだと見られることを承知の上で、執筆されたものである。
問題は、ここからである。
この投稿者である大鹿屋は、朝日の関係者で、「私憤によって、著者である宇留間を貶めようとしたのではないか」という話があった。そうなると僕の関心はずいぶん変わる。
大鹿靖明という人物が朝日におり、それは経済部の記者である。
朝日新聞の言論サイト「論座」に、その記者のプロフィールが出ていた。
「1965年、東京生まれ。早稲田大政治経済学部卒。ジャーナリスト・ノンフィクション作家。88年、朝日新聞社入社。著書に第34回講談社ノンフィクション賞を受賞した『メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故』を始め、『ヒルズ黙示録 検証・ライブドア』、『ヒルズ黙示録・最終章』、『堕ちた翼 ドキュメントJAL倒産』、『ジャーナリズムの現場から』、『東芝の悲劇』がある。近著に『金融庁戦記 企業監視官・佐々木清隆の事件簿』。取材班の一員でかかわったものに『ゴーンショック 日産カルロス・ゴーン事件の真相』などがある。キング・クリムゾンに強い影響を受ける。レコ漁りと音楽酒場探訪が趣味」
僕が目をとめたのは、受賞歴や出版歴ではなく、このプロフの最後にある「レコ漁りと音楽酒場探訪が趣味」という部分だった。
なぜならば、前出の、アマゾンの投稿者の「大鹿屋」のプロフには、「音楽酒場探訪家、安レコ収集家 | ひ・み・つ」とあったからだ。
大鹿靖明と大鹿屋。そして、「レコ漁りと音楽酒場探訪が趣味と音楽酒場探訪家、安レコ収集家」。
これは偶然の一致なのか? それとも、このレビューは、朝日新聞の現役記者、大鹿靖明が書いたものなのか?
疑心暗鬼になった僕は、すぐさま朝日新聞社の代表電話に連絡をした。
「記者におつなぎすることはできません。広報部におつなぎすることもできません」と電話口の女性は話し、読者からの電話対応をしている「読者オフィス」なる部署に回された。
質問の要点は、このアマゾンレビューの大鹿屋なる人物は、大鹿靖明なのかという点と、そうだった場合、朝日としてはどうなのかということである。後述するように、朝日からは明確な回答は得られていない。
朝日新聞の現役の記者が、アマゾンのレビューに著者批判をして悪いわけではない。しかし、その投稿の意図には関心を持たざるを得ない。
宇留間に話を聞くと、宇留間は、過去にこの大鹿靖明が、朝日の社内規定を無視して出版を行なったという経緯について、話した。
むろん僕は、当時のその事件とやらを知るわけもなく、宇留間の言い分を鵜呑みにするわけにもいかない。
しかしである。もし、このレビューの主、大鹿屋なる人物が大鹿靖明であったとして、過去にそのような因縁があったのであれば、このレビューの持つ意味はずいぶん変わってくるではないか。大鹿屋は、過去の恨みから逆襲してきたのか。
現役の記者が、twitterで持論をぶちまけたときにバッシングを受けたり、市議会議員などが、匿名で投稿したものが暴露されて問題になったケースなどは、近年いとまがない。そういった倫理について、朝日もずいぶん記事にしている。
そもそも僕は、SNSとやらで匿名で攻撃をする風潮を気持ち悪く思っている。新聞記者ならば、正々堂々と実名で、正面からやれと言いたい。
大鹿の名前を使わず、職業も書かず、その一方で、大鹿屋という自分の名前の一部を入れたハンドルネームで投稿していると考えればこそ、むしずが走るわけだ。それを、わざわざ、宇留間が書いた本に、レビューとして投稿している。これを、姑息な嫌がらせと言わずになんと言おう。過去に因縁のある人物に対して、匿名で人格批判をするのは、きわめてゲスなやり方である。
封建的な時代であれば、「武士の風上にも置けない」と表現されよう。
ちなみに、「風上にも置けない」というのは、「風上に置いてしまうと臭気が流れて来て、我慢もできない」ということより、「卑劣な人間をののしっていう言葉」なのだそうであるから、僕のいまの気分を表すのに、言い得た表現である。
最初に対応した朝日新聞社の「読者オフィス」のノセと名乗る人は、僕の質問をよく理解した感じがあった。数日後の11月16日に電話したときに、応対してくれたヤマダという人物は、僕の質問を途中で遮り、「これはアマゾンがどうするかの問題」だと言った。またその後に応対したカワタは、このレビューが朝日記者のものならば問題があるとの認識を示したが、自分では結論を出せず広報が判断するとのことだった。しかし、朝日から連絡はなくスルーされている状態である。
本人の投稿なのかどうかなど、すぐに確認できるはずだが、それをしないところをみると、朝日は、この程度の問題として放置するつもりだと受け止めた。
宇留間にしろ、僕にしろ、これは大鹿靖明と朝日新聞社から、顔に泥を塗られた、いや、挑戦状を叩きつけられたに等しい。
このままで済ますわけにはいかない話になっている。
文責/木村浩一郎